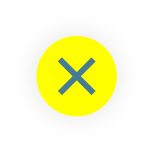体験企業レポート


株式会社 ホンダカーズ東白川
企業紹介
白河市と棚倉町に拠点を構える地域密着型のカーディーラー。「カーライフ」だけでなく「ライフ」そのものを豊かにすることを目指し、気軽に立ち寄れる居心地の良い店舗づくりに力を注いでいる。車の相談はもちろん、キッズコーナーやリラックススペースを備え、家族で楽しめる空間をご提供。「待ち合わせのできるお店」を合言葉に、地域の皆さまの日常に寄り添い続けている。
採用課題
短期的に求人媒体への掲載を利用したものの、成果が定着せず、採用活動の持続性が課題となっていた。また、地域に根差したエリア採用を強化する必要性がありながら、説明会の実施経験がなく、そのノウハウが不足している点も課題。さらに、中途採用者が多く、現在の採用は社員からの紹介(リファラル採用)に依存している状況で、自社の採用手法を確立していく必要がある。
コーディネーター
株式会社東邦銀行 法人コンサルティング部/福島学院大学 客員教授 木村信綱 氏
■プロフィール/福島学院大学の情報ビジネス学科で23年間にわたりデザイン教育に携わり、企業や団体と連携し「まちづくり」、「商品開発」、「情報発信」、「イベント企画運営」など年間を通して60件以上の地域連携プロジェクトを展開。企業や地域の魅力を見つけ出し、学生を絡めて様々な角度から地域振興につながる意見を引き出していくことが得意。
■支援内容/多角的な採用手法を学び、自社に適した手法を選定。ペルソナを議論し、求める人材に響く情報発信を実践レクチャー。
STEP1
地域密着型採用戦略の新たな一歩
2024年9月13日
現場見学と現在の採用状況について
1回目は会社見学をした上で、現在の採用状況の整理と課題の洗い出し、リファラル採用の活用や新卒・中途採用の方向性について議論が行われました。
<採用状況の整理と課題の洗い出し>
まず、現在の採用状況について整理した結果、以下の課題が浮かび上がりました。
・中途採用が中心であり、新卒採用の経験が少ない
・大手求人媒体を活用したが、定着しなかった
・エリア採用を強化したいが、説明会などのノウハウがない
・社員紹介による入社(リファラル採用)が多い
この状況を踏まえ、リファラル採用の制度整備、新卒採用の方針策定、企業の魅力発信の方法を具体化していく必要があると感じられました。
<リファラル採用の活用と強化>
現在、社員紹介による採用が一定数あるため、リファラル採用のインセンティブを明確化し、活用を推進する方針が検討されました。
・紹介した社員がより積極的に声掛けできるよう、紹介だけでもインセンティブを付与
・カジュアル面談や職場見学を通じた応募のハードルを下げる
・会社全体で「採用意識」を共有し、営業職2名の募集を明確に伝える
リファラル採用の可視化を進めることで、「仲間を自分で連れてくる」文化を根付かせることが重要であるとの認識が共有されました。

採用戦略ディスカッション
現在募集している職種としては、整備士職と営業職。
その中でも営業職を積極的に募集していきたいとのことで、職種に見合うターゲットの整理を行いました。
<求める人物像と採用ターゲットの明確化>
まずは、「どのような人物を採用すべきか?」についての整理から行われました。
[求める人物像]
・「お互い様」の精神を持ち、助け合いができる人
・自ら悩みを相談し、周囲とコミュニケーションを取れる人
・「どうすっぺ?」と話し合いながら、主体的に動ける人
このような整理を通じて、社内での採用基準を統一し、適切な求職者に向けたアプローチを行う重要性が再確認されました。
<新卒採用の方向性>
特に営業職の新卒採用について、以下の課題が見えてきました。
[課題]
・営業職の新卒希望者が少ない
・ディーラーの仕事に対する「ノルマが厳しい」というイメージがある
・高卒採用は一定数あるが、大卒採用は難航
「営業=厳しい」という印象を払拭するための情報発信が必要であり、実際の業務内容や成功事例を積極的に伝えることで、安心感を持たせることが重要であることが見えてきました。
<今後の方向性と次回議題>
最後に、次回のディスカッションに向けた議題が整理されました。
・新卒採用のペルソナを明確化し、その層にどう情報を届けるかを検討
・高校や地域の学生との接点を増やす方法を模索
今回のディスカッションでは、採用の現状と課題を整理し、リファラル採用の活用、新卒・中途採用の方向性、求める人物像の棚卸しなど、多岐にわたる議論が行われました。
STEP2
理想のペルソナ像を明確化
2024年10月11日
求める人材像(ペルソナ)の明確化
2回目では、前回の内容を踏まえ、ターゲットとなる「ペルソナ」の具体化と、それに基づく求人アプローチの方向性を議論しました。
木村氏のファシリテーションのもと、社内で「どのような人物と働きたいか」について意見を交わしたところ、以下の共通点が浮かび上がりました。
趣味:アウトドアが好きな人(既存社員にもアウトドア派が多い)
体型:自己管理ができる人
日課:お酒が好きな人(必須ではないが、コミュニケーションの場としての側面を考慮)
映画の好み:アクション映画など、シンプルで前向きなストーリーを楽しめる人
将来の夢:家庭を持ち、仕事と両立できる環境を求める人
これらの特徴を踏まえ、「家庭と仕事を両立できる職場」というメッセージの打ち出しが有効と考えられます。
<Uターン希望者へのアプローチ方法>
ペルソナを考えた際、その人の現在の居住についても話し合われました。首都圏で働いていて、地元に帰ってきたい30代層も狙っていきたいといった意見が出る中、福島県内限定の発信では上記ターゲットに届かない可能性があるため、以下のような手段も提案されました。
・親世代を経由する:県内に住む親から子どもへ情報を伝えるルートを模索
・広告の掲出場所:帰省時に訪れる可能性の高い場所を選定
- ラーメン屋、神社、居酒屋、コンビニ、ガソリンスタンド、新幹線の止まる駅など
・キャッチコピーの工夫
- 例:「そろそろ実家に戻りたいあなた、ホンダカーズで一緒に働きませんか?」
ぼんやりとしたイメージはあっても、一緒に働きたい仲間を具体的に想像することがほとんどなかった社員の皆さん。はっきりとしたイメージを出すことに時間を要しましたが、このように書き出していくことで徐々に人物像が出来上がっていきました。

求人媒体の選定
次に、ディスカッションで出たペルソナに対して、どのようにアプローチすれば求人情報が響くか話し合われました。
実際に求人を検索してみた結果、転職意思が強くない人にとっては会員登録が必要なサイトは面倒という意見も。また、潜在的な転職ニーズを引き出すため、求人の掲載先を慎重に選ぶ必要があることがわかりました。
<参加者の感想>
Yさん:「求人を見る人によって響くポイントが違うため、ペルソナの明確化が最優先だと再認識した」
Kさん:「見る人によって求人の受け取り方が異なると実感。一画面の目立つ位置に重要な情報を載せるべきだと感じた」
Mさん:「年収や年間休日など、具体的な数字に注目する傾向があると気づいたため、キャッチコピーに盛り込めればと感じた」
今回の議論では、求める人材像を具体的に言語化し、それに基づいた求人アプローチの方向性を検討しました。ペルソナ設定の重要性が改めて認識されるとともに、求人の発信方法や媒体の選定に課題があることが明確になりました。次回は、より具体的なターゲットを絞り込み、効果的な採用施策を話し合います。
STEP3
採用戦略の次なる一歩へ
2024年11月14日
ペルソナの確定と打ち出し方について
今回の議題は、採用活動の具体化として「ペルソナの確定」「求人の打ち出し方の方向性」「高校生へのアプローチ」の3点が主軸となりました。
<ペルソナの確定>
営業職の採用ターゲットとして、前回の話し合いを振り返りつつ以下の2つの人物像を設定します。
・高卒・35歳(県南エリア在住、既婚・子持ち、接客業経験あり)
転職理由:安定した収入とキャリアの充実
懸念点:家族の反対や生活スタイルの変化
対策:夫婦での会社見学受け入れ、収入変化の可視化
・大卒・25歳(県南エリア出身、現在は首都圏在住、未婚)
転職理由:地元での生活志向、キャリアの再考
懸念点:地方での人間関係や生活の変化
対策:都会との比較メリットを強調(時間の余裕、家族との距離など)
<求人の打ち出し方の方向性>
高卒向けは地元エリア、大卒向けは首都圏をターゲットとし、それぞれの関心に合わせたメッセージを作成。例えば、地元へのUターン転職を促す場合は「里帰り転職」などのキャッチコピーが効果的です。
また、求人情報を社内に掲示し、社員からのフィードバックを受けながら内容をブラッシュアップする方針となりました。

社員の想いが込められた採用活動に向けて
今後は、決定したペルソナに基づき求人原稿を作成し、有力な求人媒体に掲載する方針となりました。
その際に、地元に住む求職者とUターンを考えている求職者に向けての2パターンの原稿を作成し、反応などを見ながらブラッシュアップが必要となります。
<参加者の感想>
Tさん:「採用は単に求人を出すだけではなく、奥深いものだと学んだ」
Kさん:「求人について勉強になる良い機会だった」
Mさん:「今必要な人材を理解し、考えを共有できた」
Fさん:「採用に対する社員の積極的な関与が重要であると実感。課題も見え、今後が楽しみ」
STEP4
成果とまとめ
ペルソナ設定による採用戦略の再構築と実質的成果
今回はペルソナの具体化により、社内で人材像の共通認識が図られ、「同じ人材を求めていると思っていたが、実際は異なっていたことに気づいた」と感想の声が聞かれました。
求人票は地元向けと首都圏向けの2種を作成し、それぞれの特性に合わせたメッセージ発信を実施。
今回はAirワーク・indeedプラスへの掲載を行ったが、1ヶ月で3名の応募がありました。
「採用」という大きな枠組みの課題からひとつずつ課題を細分化できたことで、次なる展開も見えてきたと言います。
採用に対する視野の広がりも見られ、採用力の強化と意識改革に繋がる成果となりました。
<まとめ>
今回の伴走支援を通じ、自社に合う人物像を社員みんなで話し合い、可視化することで、その未来の仲間に向けて何をどのように発信するべきかが見えてきました。
今後は、これらの施策を実践しながら、効果を検証し、改善を重ねていくことで、自社に最適な採用方法が確立されていくことが期待されます。地域特性や求職者のニーズを踏まえた独自の採用戦略を築き上げることで、長期的に優秀な人材の確保につながるでしょう。